
【この記事を書いた人】
- グレー発達症ADHD/ASD
- うつ病、対人恐怖症を克服
- 工場歴10年
- 転職歴10回
詳しいプロフィール
はじめまして「トシ」です。
私は自閉スペクトラム症(ASD)の特性が強いグレー発達障害で、人間関係に馴染めない「社会不適合者」です。
そのため、学生時代から人間関係をうまく築けず、中学・高校では部活の先輩からいじめを受け、次第に対人恐怖症を抱えるようになってしまいました。
高卒でフリーターになるも、要領が悪く、社交スキルが足りなかったため、接客業といった仕事はとてもできませんでした。

「自分にできる仕事はない」と本気で思ってた。
「全部、自分のせいだ」と責め、しだいに食欲もなくなり、うつ病を患ってベッドでただ横たわる日々。。
しかし今では、本の知識からあらゆる障害を理解し、行動を少しづつ積み重ね、働くための自信を取り戻しました。
うつ病を薬ナシで克服し、実家を離れて幸せに一人暮らししています。
そして、工場で働くこと10年で、10回の転職を経験してきました。
こうして働いていると、どの工場の業種が適しているかも自然に分かってきました。
そういった経験から、、
- 働きやすい工場を見つける方法
- 自信をつけるための方法
- 他人を気にしなくなる方法
などの情報発信をしているので、お役に立てればと思います。



それでは、よろしくお願いします!
こんな悩みありませんか?
他人が怖くて仕事ができない。。
なるべく人と関わらない仕事がしたい。。
ボクもそう感じていましたが、、
現在は、働きながら一人暮らしまでできるようになりました。
この記事を読むことで、他人が怖い理由が分かり、他人が怖くてもできる仕事を知れます。
結論:他人が怖く感じる人は、製造工場で働きましょう。
その前に「愛着スタイル」と「パーソナリティ障害」を理解しないことには話が進みません。
理解を進めるために、かみ砕きながら説明するので、上から順に読んでくださいね。
愛着スタイル:養育者の影響で幼い頃に作られた性格
愛着スタイルの4タイプ:
- 安定型:養育者が子どもの感情やニーズに応じた対応を与えたことにより、健康的な人間関係を築きやすい。
- 不安型:養育者が過保護で注意を引く行動を強制したことにより、環境相手に依存しすぎたり、過度に確認を求める。
- 恐怖型:養育者が子どもに対して愛情とともに恐怖を与えたことにより、人間関係において混乱・不安を抱えやすい。
- 回避型:養育者が感情的に無関心だったり、拒絶的だったことにより、相手を遠ざけたり、孤独を好む傾向がある。←この記事で解説しています。
一匹狼スタイルも、この辺から出来上がるんですね。
ボクの家庭は深く喋らない家族なので、回避性愛着スタイルになりました(笑)
まとめ:「回避型愛着スタイル」は相手を遠ざけたり、孤独を好む傾向があるので”接客仕事”は不向き。
パーソナリティ障害:性格がゆがみ過ぎた状態
性格というのは十人十色で、他人と関わるのがニガテな人、自己中な人、かまってちゃんな人などがいますよね。
そういった性格も、度を越してしまうと「パーソナリティ障害」となります。
パーソナリティ障害の10タイプ:
- 妄想性:他人への強い不信感や疑念を抱きやすい。
- 統合失調型:社会的な孤立や奇妙な考え方、行動が目立つ。
- 統合型:奇妙な思考や行動、会話パターンを示す。
- 反社会性:他人の権利を無視し、攻撃的で反抗的な行動をとる。
- 境界性:感情の不安定さ、自己イメージの歪み、対人関係の不安定さ。
- 演技性:過度な注目を求め、劇的な行動をとる。
- 自己愛性:自己中心的で他人に対する共感が乏しい。
- 依存性:他人に過度に依存し、自立することが難しい。
- 強迫性:完璧主義や過剰な秩序志向が特徴的。
- 回避性:拒絶や批判を恐れ、対人関係を避ける傾向が強い。←この記事で解説しています。
性格でも、日常生活・社会生活に影響を及ぼす状態・状況になると”障害”になるんですね。
そして、次は「回避性パーソナリティ障害」を主に解説しますね。
回避性パーソナリティ障害=他人が怖い人
他人に対する恐怖心・拒絶される不安から、社会的な関わり・対人関係を極力避ける傾向が強い”パーソナリティ障害の一つ”です。
単なる内気・恥ずかしがり屋とは異なり、本人の日常生活・社会生活に深刻な支障をきたします。
個人の性格や行動の特徴が極端になったために、日常生活や対人関係に支障をきたします。
回避性パーソナリティの根底にあるのは”自己肯定の低さ”です。
根底:
- 他人と関わることによる緊張感や不安感が強い。
- 孤独を感じながらも、関係を築くのが怖いため、孤立しやすい。
- 批判や拒絶に対して極端に敏感。
対人関係面:
- 他人に拒絶されることや、批判されることが怖い。
- 恥をかくのが怖くて、自分をさらけ出せない。
- 親しい関係を築くことが困難で、人付き合いを避けがち。
自己評価面:
- 強い劣等感を抱いており、自分が他人より劣っていると信じている。
- 自分が他人に受け入れられない存在だと感じる。
- 小さなミスや失敗に対して過剰に自分を責める。
行動面:
- 批判や拒絶の可能性がある状況を避ける(例: 新しい職場やグループへの参加をためらう)。
- 新しい挑戦や責任を伴う仕事を引き受けるのを恐れる。
- 安全な環境や人間関係に固執しがち。
仕事や社会生活面:
- 営業、接客、電話応対、スピーチが苦手
- 他者からの評価を恐れ、仕事や学業で積極性に欠ける。
- 新しい職場環境や、社会的集団に馴染むのが難しい。
- 人と協力することに不安を感じ、結果的に孤立しやすい。
このように、日常生活や仕事において大きな困難を感じることがあります。
まとめ:「回避性パーソナリティ」と「回避型愛着スタイル」の違い
ボクも混同してしまうので、おさらいとしてまとめました。
回避型愛着スタイル:一人好き。他人といると居心地が悪い。
- 特徴:人と親密な関係を避ける傾向があり、特に恋愛や家族など、親密な人間関係で距離を取りたがる。
- 原因:幼い頃の両親による無関心や、拒絶による影響。
回避性パーソナリティ障害:他人が病的に怖い。強い自己否定。
- 特徴:批判や拒絶への恐怖心が強く、広範囲の対人関係や社会的状況を避ける。
- 原因:幼少期の厳しい批判や拒絶的な経験、遺伝的要因、トラウマ。
似ているけど、少し違いますよね。
性格は受け入れ、生きやすい仕事・生活を選ぶのがベスト
なぜなら、性格そのものを治すのは困難で、物事の考え方を変える「認知行動療法」など、精神科でシッカリ治療をしなければならないためです。
それに、回避性パーソナリティなら相手に迷惑をかけることはないので、自分一人で楽しむというのもアリかなと思ってます。
実際にボクは、、
- 一人カラオケ:他人に気を遣わず、時間いっぱい歌える
- カフェでブログ書く:時間を有意義に使える
- 読書:勉強ができる
- 筋トレ:自分を磨ける
このように、おひとり様ならではの楽しみ方で人生を謳歌しています。
「障害」とはあくまで「日常生活・社会生活に影響を及ぼす状態・状況」です。
逆に言うと、生活ができるのなら障害ではなくなるということ。
なので、そこまで悲観する必要はないかと思います。
「他人が怖い」にもメリットがある
メリットを知ることで「こんな自分でも良いんだ。」と受け入れることができます。
自己防衛能力が高い
- 他人に対して慎重になるため、危険な人や状況を避けやすい。
- 初対面の人に対して距離を置くことで、トラブルに巻き込まれるリスクを減らせる。
相手を観察する能力が養われる
- 他人を怖いと感じることで、人の言動を慎重に観察する力がつく。
- 相手の気持ちや意図を読み取るスキルが向上し、深い人間関係を築きやすくなる。
謙虚さが保たれる
- 他人を恐れることで、自分を過信しすぎず、謙虚な態度を持ちやすい。
- 人に頼りすぎず、自立した行動が取れる。
信頼関係を大切にするようになる
- 他人が怖い分、信頼できる人との関係をより慎重に育てる意識が強くなる。
- 表面的な関係ではなく、深い絆を重視するようになる。
無駄な交際を避けられる
- 人付き合いに慎重になるため、本当に必要な人間関係だけを維持できる。
- 無理に多くの人と関わるストレスから解放される。
自己成長のきっかけになる
- 他人を怖いと感じる理由を内省することで、自分の弱点や課題に気づくことができる。
- 社交スキルを磨く努力をすることで、成長につながる。
時間とエネルギーを有効活用できる
- 無駄な人間関係を避けることで、仕事や趣味など自分の大切なことに集中できる。
物事には悪い面もあれば、良い面もあります。
このように視点を変えるだけで、自己成長やリスク回避に役立つのです。
そもそも「他人が怖い」という警戒心は、危険が迫ったときに”身を守るための手段”なのです。
おそらくですが、あなたが昔に他人に傷つけられて、警戒することで心を守ってきた経験があるはずですよ。
そばにいつもいてくれたボディーガードのような”心のあなた”に感謝するのもいいですね。
ここまで読んで「なぜ他人が怖いのか?」という心のモヤモヤが解けてきたと思います。
精神科医がオススメする適職
ボクは普段から精神科医の方の本をよく読むのですが、「他人が怖い人の仕事」を選ぶ基準は、、
選ぶべき職業
- 毎日決まった場所・ルーチンワーク
- 自分に分担された仕事に、じっくりと取り組めるようなもの
選んではいけない職業
- 強すぎる刺激・感情的なやりとり。
- 争いごとの解決・対人折衝が中心を占める。
- 競争・ノルマがある。
- 素早い判断・迅速な行動を求められる。
このように語っており、これにはボクも同意。
ここからは、精神科医がオススメしている適職を紹介しますね。
「これは万人には当てはまらないと思う。。」と感じた職業は省いています。
専門資格職:文書作成・手続きが中心
- 法書士
- 行政書士
- 土地家屋調査士
- 社会保険労務士
医療系資格職:キッチリ手順があり、人間関係がシンプル
- 臨床検査技師
- 言語聴覚士
- 理学療法士
- 眼鏡士
事務職:汎用性が高く、つぶしがきく
- 経理
- 法務
- 総務
- 物品管理
- 施設管理
これらは、ある程度経験を積むことで、他でも使える汎用性のあるスキルを身に着けることが可能。
電話応対・接客がある
技術職:社交面ではなく、技術面が評価される
- 技能職
- 職工
- 職人
- 現場技術者
販売・営業系:扱う商品に関心があるなら可能性アリ
多趣味な人ではなく、一つの領域をじっくり深めるなら試すのもいいかも。
作業員:専門技能・経験要らず
- 工場
- 施設
- 倉庫
- 現場
- 保守管理
こんな感じです。
ボク的には「製造工場」がオススメ
というのも、精神科のオススメする職業であると同時に、対人恐怖が強いボクでも長年続けてこれた職業だからですね。
理由はこちらの記事にまとめています。
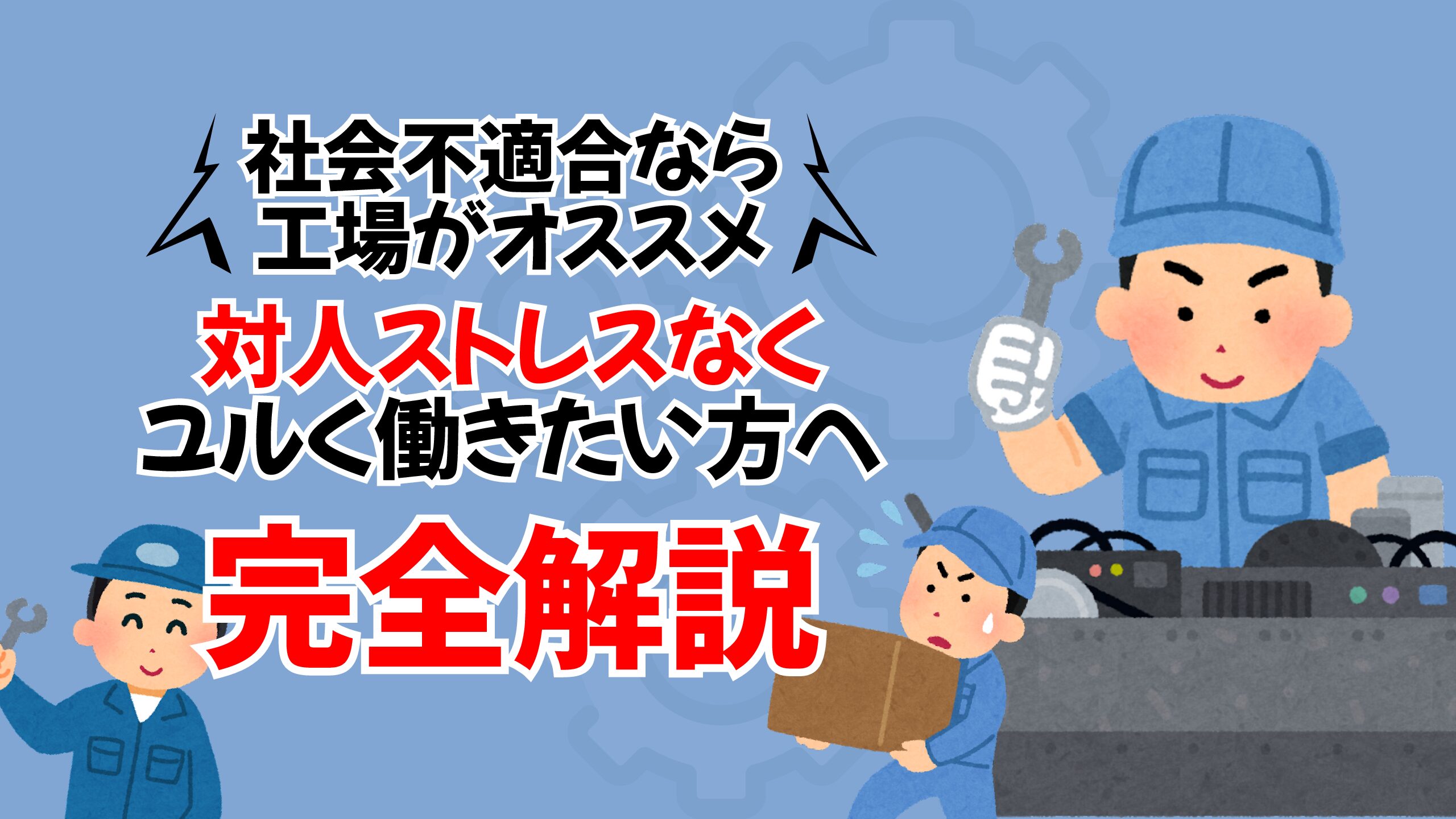
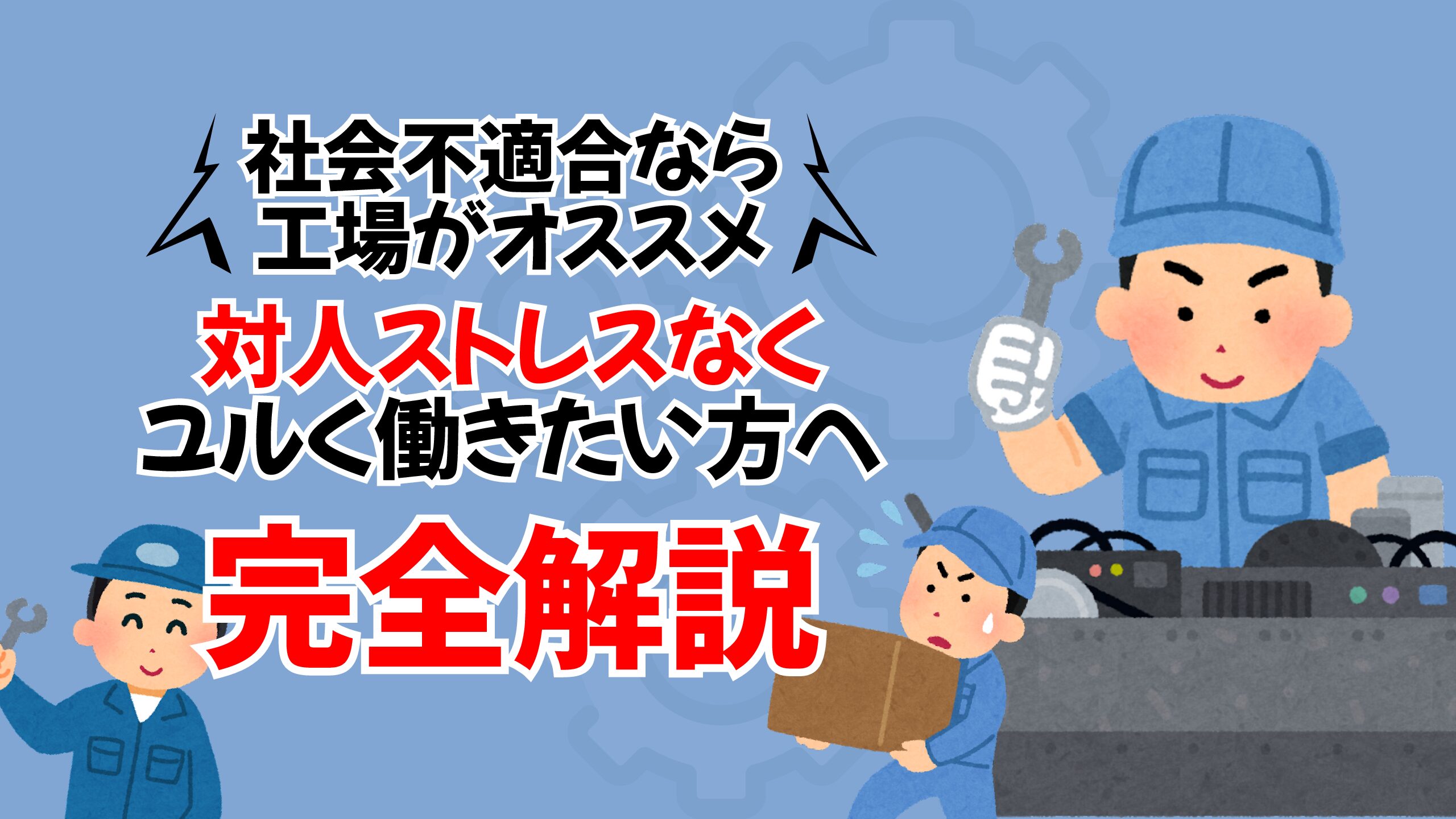
もし、職業に迷っているならとりあえずやってみるのもアリかなと思います。
回避性パーソナリティが増加している背景には、日本が少しずつ冷たい世界へ順応するための変化なのかもしれませんね。
その前に、あなたの居場所を早いうちに見つけておくのは本当に大事なことです。
「本業+副業」というバランス派を選ぶと良い
- 本業=ストレスは大きいが、時間がかからずにお金は手に入る。
- 副業=時間はかかるが、ストレス最小で大きく稼げる。
ボクは上の理由から、2面を上手に補う働き方を選んでいます。
最悪、どっちかがダメでも働いていけるようになってるのがグッド。
この記事を読んでいただき、ありがとうございました。